今回は、漏電火災警報器の一般構造についてです。
ポイント!!
漏電火災警報器の一般構造と装置全般機能・表示がわかります!!
乙7用漏電火災警報器の法令や設置基準の詳細はこちらに詳しく書いていますので、参考にしてください。
はじめて行きましょう!!
目次
一般構造と機能
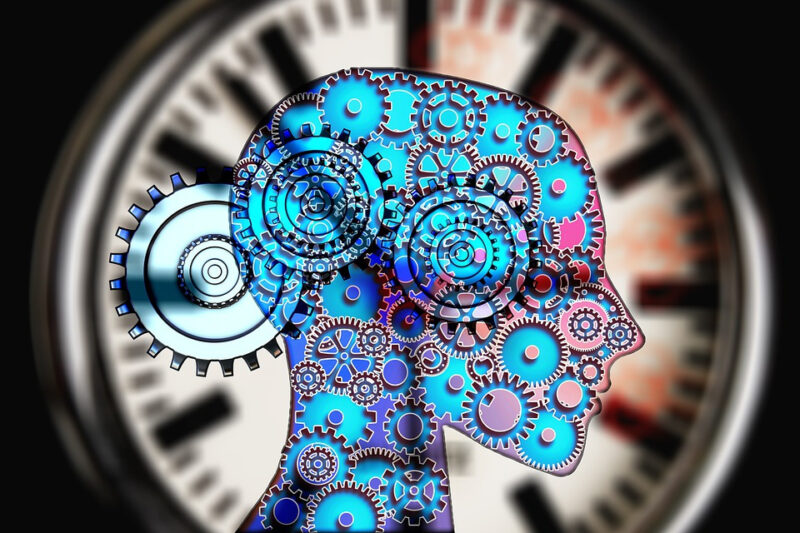
漏電火災警報器の主構造と機能は次の6つです。
- 良質材料で、配線・取付が簡単かつ確実
- 耐久性があって、雑音・障害電波は自ら出さない
- 充電部は外から簡単に人が触れない、もしくは十分に保護されている
- 端子は電線(接地せん含む)を簡単、かつ確実に接続ができて、適当なカバーがあること(でも、接地端子および配電盤に取り付ける埋め込み式は除く)
- 端子部以外は堅牢なケースに入っていること
- 定格電圧が60Vを超える変流器または受信機の金属ケースは、接地端子があること。
こんなところですが、半分は電気を知っている方なら当たりまえのことかと思います。
特に電気工事士に合格していれば、なおさらです。
装置全般としては、次の5つが挙げられます。
- 音響装置
- 2本の電線を受信機に接続したものいう。
定格電圧の90%の電圧で音を発する必要がある。
定格電圧における音圧は、無響音で定位置に取り付けた音響装置の中心から1m離れて70dB以上。
無響音の定位置とは、音響装置を受信機内に取付けられる位置が多い。
絶縁抵抗は5MΩ(直流500Vをかけて)以上。
警報音を断続するものは、休止時間2秒以下・鳴動時間は休止時間以上は必要、つまり2秒の休みであれば、2秒以上は鳴らす必要がある。
定格電圧で8時間連続で鳴らすもの - 電磁継電器
- リレー:変流器から漏電電流が受信機に入って増幅され、その電流によって電磁継電器が開閉して、警報ブザーやランプが動作する。
塵埃などが簡単に侵入しない構造。
接点部は、外部負荷と一緒にしてはいけない、ただし、外付音響装置用接点にこの限りではない。 - 電源変圧器
- 容量は、定格電圧における最大負荷電流、または設計上の最大負荷電流の連続に耐えること。
- 表示灯
- 電球のみは、定格電圧の130%の交流電圧を20時間連続して使った場合、断線・光束変化・黒化・電流低下が生じないこと。
電球を2つ以上の並列回路に接続、ただし電球ので、放電灯・発光ダイオードは関係がない
周囲環境300lx・前方3m離れた地点で明確に識別できること。 - スイッチ
- 簡単で確実に作動、停止場所が明確であること。
接点の容量は最大使用電流に耐えること。
機能・表示
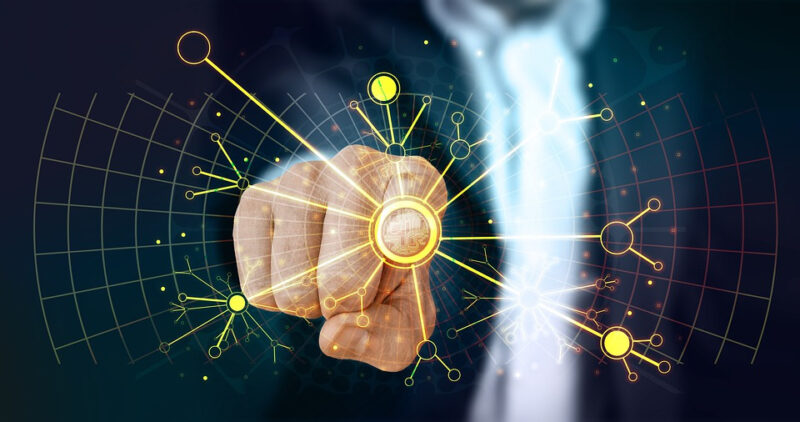
機能としては、次の3項目です。
- 公称作動電流値は200mA以下、ただし感度調整装置がついているものは、調整範囲の最小値以下であること。
- 感度調整装置がついているものは、調整範囲の最大値は、1A以下。
- 漏電火災警報器が動くのに漏電電流値の値は製造者によって表示されている。
共通の表示事項としては、次の5項目です。
- 届出番号
- 定格周波数(受信機の場合は電源周波数)
- 製造年
- 製造者名
- 商標、または販売者名
変流器のみの表示事項としては、次の6項目ありますが、詳細は次の記事にのっています。
受信機のみの表示事項としては、次の10項目ですが、詳細は次の記事にのっています。
以上で、漏電火災警報器の構造・機能の一覧です。
例題

問題1
規格法令上、変流器に表示しなくてもよいものはどれか?
- 届出番号
- 製造年
- 製造番号
- 製造者名・商標、または販売者名
解答・解説1
変流器に表示する必要があるものは、次の8項目です。
- 「漏電火災警報器変流器」という文字
- 届出番号
- 「屋外型/屋内型」の文字
- 定格電圧・電流、定格周波数・「単相/三相」の文字
- 設計出力電圧
- 製造年
- 製造者名・商標または販売者名
- 極性を示す記号
ここ以外に挙げられているのは、3の「製造番号」です。
なので、正解は「3」となり、製造番号は表示しなくてもよいことになります。
続いて、もう1問です。
問題2
漏電火災警報器の感度調整装置の最大値は、規格省令で定められているのはどれ?
- 0.2A
- 0.4A
- 1A
- 1.2A
解答・解説2
感度調整装置がついている漏電火災報知器は、調整範囲の最大値は1A以下と定められています。
よって正解は、「3」となります。
漏電火災警報器は、消防設備士試験 乙7のキモのところなので、しっかり覚えておく必要があります。今回は構造・機能ですが、この他に防火対象物に関する設置基準などもよく問題がでるので、抑えていく必要があります。
最後は、電気的な設置基準について、書いていければと思います。ここまで抑えておくと、電気工事士を合格していれば、なんとかなるのでは?と思います。








