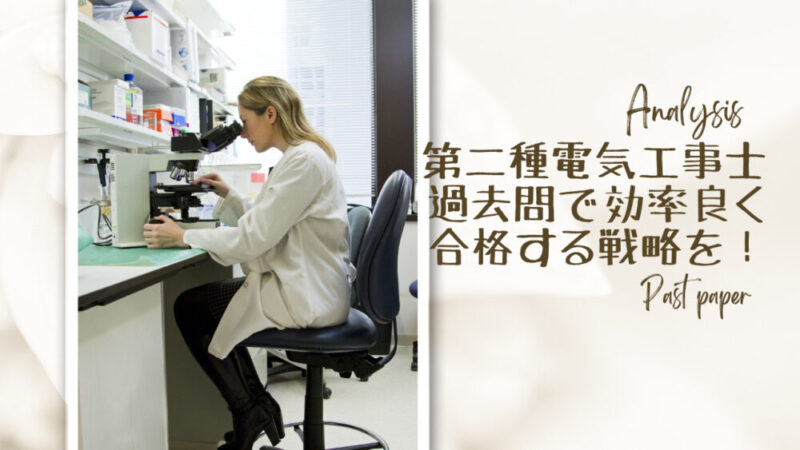- 電線の許容電流の出題ポイントを教えて!
- 電線の許容電流の問題って毎回出題されているのは本当?
- 現場で実際に使えるの?
電線の許容電流の問題は電気工事士2種筆記試験ではほぼ毎回出題されています。勉強をし始める分野にはうってつけの範囲です。電気工事士2種は計算問題より暗記が多い資格ですから。
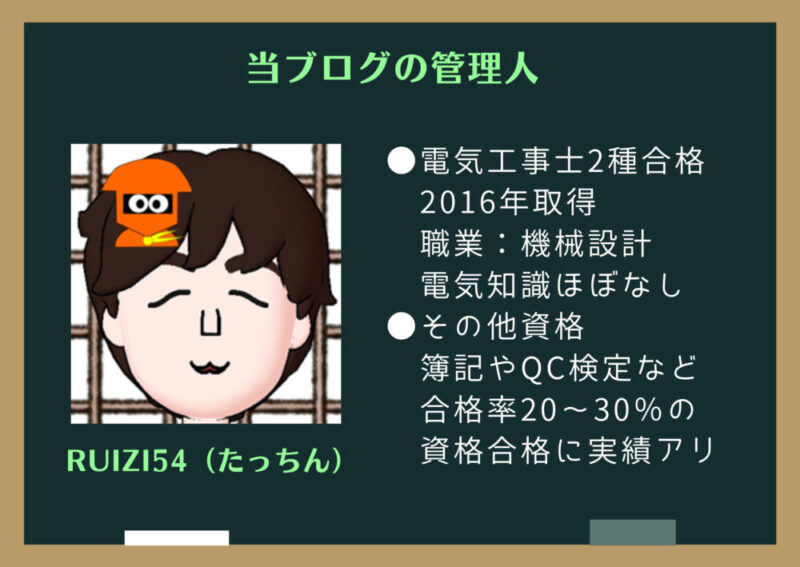
この記事では、電線の許容電流が重要な問題であること、そして出題ポイントの把握ができます。この記事を読むことで、筆記試験対策の暗記ポイントをサクッと理解できます。
今回はさらに実際に使う場面についても解説していきます。

実際の現場でも電線サイズを決めるために許容電流値はよく考えているよ!
電線の許容電流は、電線サイズと管内の電線本数が命!この2つの重要事項をきっちり押さえることで、ほぼ確実に問題が解けます。
毎回出題される電線の許容電流の問題とは?

令和4年(上期「午前/午後」)の2回、令和3年(上期「午前/午後」・下期「午前/午後」)の合計4回、令和2年の2回、令和元年の2回の合計10回の過去問を調べました。結果、毎年同じような問題と選択肢で構成されています。
| 出題年度 | 問題番号 | 問題文 | 回答群 | 備考 |
| 令和4年 (上期午前) | 8 | 金属管による低圧屋内配線工事で,管内に直径2.0 mmの600Vビニル絶縁電線(軟銅線) 4本を収めて施設した場合,電線1本当たりの許容電流[A]は。 ただし, 周囲温度は30 ℃以下, 電流減少係数は0.63とする。 | イ.22 ロ.31 ハ.35 ニ.38 | 令和元年(上期)の 問題と近い! |
| 令和4年 (上期午後) | 8 | 金属管による低圧屋内配線工事で,管内に直径2.0 mmの600Vビニル絶縁電線(軟銅線)2本を収めて施設した場合,電線1本当たりの許容電流[A]は。 ただし,周囲温度は30 ℃以下,電流減少係数は0.70とする。 | イ.19 ロ.24 ハ.27 ニ.35 | 令和元年(上期)の 問題と近い! |
| 令和3年 (下期午前) | 8 | 低圧屋内配線の合成樹脂管工事で、管内に直径2.0mmの600Vビニル絶縁電線(軟同線)を4本納めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流値[A]は。 ただし、周囲温度は30℃以下とする。 | イ.17 ロ.19 ハ.22 ニ.24 | |
| 令和3年 (下期午後) | 12 | 許容電流から判断して、公称断面積1.25mm2のゴムコード(絶縁物が天然ゴムの混合物)を使用できる最も消費電力の大きな電熱器具は。 ただし、電熱器具の定格電圧は100Vで、周囲温度は30℃以下とする。 | イ.600Wの電気炊飯器 ロ.1000Wのオーブントースター ハ.1500Wの電気湯沸器 ニ.2000Wの電気乾燥機 | 令和2年(下期午前)と全く同じ問題! |
| 令和3年 (上期午後) | 8 | 低圧屋内配線の合成樹脂管工事で、管内に断面積3.5mm2の600Vビニル絶縁電線(軟同線)を3本を納めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流値[A]は。 ただし、周囲温度は30℃以下とする。 | イ.19 ロ.26 ハ.34 ニ.49 | |
| 令和3年 (上期午前) | 8 | 合成樹脂製可とう電線管(PF管)による低圧屋内配線工事で、管内に断面積5.5mm2の600Vビニル絶縁電線(軟同線)7本を納めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流値[A]は。 ただし、周囲温度は30℃以下、電流現象係数は0.49とする。 | イ.13 ロ.17 ハ.24 ニ.29 | |
| 令和3年 (上期午後) | 8 | 金属管による低圧屋内配線工事で、管内に直径1.6mmの600Vビニル絶縁電線(軟同線)を6本を納めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流値[A]は。 ただし、周囲温度は30℃以下、電流現象係数は0.56とする。 | イ.15 ロ.19 ハ.20 ニ.27 | |
| 令和3年 (上期午後) | 23 | 低圧屋内配線工事で、600Vビニル絶縁電srンを合成樹脂管に収めて使用する場合、その電線の許容電流を求めるための電流減少係数に関して、同一管内に電線数と電線の電流減少係数との組合せで、誤っているものは。 ただし、周囲温度は30℃以下とする。 | イ.2本 0.80 ロ.4本 0.63 ハ.5本 0.56 ニ.7本 0.49 | この回だけ、誤っているものを選択させているから注意が必要! |
| 令和2年 (下期午前) | 8 | 金属管による低圧屋内配線工事で、管内に断面積5.5mm2の600Vビニル絶縁電線(軟同線)を4本を納めて施設した場合、電線1本当たりの許 容電流値[A]は。 ただし、周囲温度は30℃以下、電流現象係数は0.63とする。 | イ.19 ロ.23 ハ.31 ニ.49 | |
| 令和2年 (下期午後) | 12 | 許容電流から判断して、公称断面積1.25mm2のゴムコード(絶縁物が天然ゴムの混合物)を使用できる最も消費電力の大きな電熱器具は。 ただし、電熱器具の定格電圧は100Vで、周囲温度は30℃以下とする。 | イ.600Wの電気炊飯器 ロ.1000Wのオーブントースター ハ.1500Wの電気湯沸器 ニ.2000Wの電気乾燥機 | 令和3年(下期午前)全く同じ問題! |
| 令和2年 (下期午後) | 8 | 金属管による低圧屋内配線工事で、管内に断面積3.5mm2の600Vビニル絶縁電線(軟同線)を4本を納めて施設した場合、電線1本当たりの許 容電流値[A]は。 ただし、周囲温度は30℃以下、電流現象係数は0.63とする。 | イ.19 ロ.24 ハ.31 ニ.49 | |
| 令和元年 (上期) | 8 | 金属管による低圧屋内配線工事で、管内に直径2.0mmの600Vビニル絶縁電線(軟同線)を5本を納めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流値[A]は。 ただし、周囲温度は30℃以下、電流現象係数は0.56とする。 | イ.10 ロ.15 ハ.19 ニ.27 | |
| 令和元年 (下期) | 8 | 合成樹脂製可とう電線管(PF管)による低圧屋内配線工事で、管内に断面積5.5mm2の600Vビニル絶縁電線(軟同線)3本を納めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流値[A]は。 ただし、周囲温度は30℃以下、電流現象係数は0.70とする。 | イ.26 ロ.34 ハ.42 ニ.49 |

問題番号までそろっているのは驚いたね!令和4年もバッチリでてるね!
直近4年で毎回出題されている電線の許容電流の問題。問題数は少ないですが、確実に1問正解をもぎとることでより合格に近づきます。問題の種類も少ないので、ぜひこの分野から勉強してください。
電線の許容電流の必須問題はこれだ!

必須問題と関係する知識を一挙にまとめます。
必須問題
問題
低圧屋内配線の合成樹脂管工事で、管内に直径2.0mmの600Vビニル絶縁電線(軟同線)を4本納めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流値[A]は。ただし、周囲温度は30℃以下とする。
選択肢:イ.17 ロ.19 ハ.22 ニ.24
解答・解説
解答
- ハの22A
解説
低圧屋内配線の許容電流値は、「電技解釈第146条(低圧配線に使用する電線)」によって規定されています。
周囲温度30℃による600Vビニル絶縁電線(IV)の許容電流は次の通りです。
単線の場合とより線の場合で変わってきます。
| 単線(直径) | 許容電流値 | より線(総断面積) | 許容電流値 |
| 1.6mm | 27A | 2.0mm2 | 27A |
| 2.0mm | 35A | 3.5mm2 | 37A |
| 2.6mm | 48A | 5.5mm2 | 49A |
| 3.2mm | 62A | 8.0mm2 | 61A |

今回は直径と言われれているので、単線の2.0mm「35A」を選びます。
また絶縁電線を電線管に4本収めていますので、電流減少係数が必要になってきます。
同一管内に存在する電線の本数によって電流の減少率が次のように変わってきます。
| 同一管内の電線数 (2本以下は減少無し!) | 電流減少係数 (3本を基準に0.07ずつ減る) |
| 3本以下 | 0.70 |
| 4本 | 0.63 |
| 5~6本 | 0.56 |
| 7~15本 | 0.49 |
今回は、4本なので0.63を用います。

2つの表は確実に覚えておいてね!
この2つの表だけで確実に正解につなげられるよ!
単線2.0mmで電流許容値35A、同一管内に配線が4本で0.63の電流減少係数なので、電線1本あたりの許容電流値は、次の計算で解けます。
35[A] × 0.63 = 22.05 ⇒ 22[A]
(少数点以下1位を7捨8入)
電線管やケーブル外装などに収めた場合、許容電流値は、「がいし引き配線の許容電流×電流減少係数(少数点以下1位を7捨8入)」で計算できます。
よって、回答は「ハ.22」となります。
周辺知識
2つの表以外に覚えておいた方がよい知識をここでまとめておきます。

一緒に暗記した方が関連づいて覚えやすいので、内容が似ているモノは一気に覚えてしまおう!
コード(VSF、VFFなど)の許容電流も覚えておいた方が良い場合があります。
| 断面積 (耐熱温度60℃) | 許容電流値 (周囲温度30℃のとき) |
| 0.75mm2 | 7A |
| 1.25mm2 | 12A |
| 2.0mm2 | 17A |
電球線には0.75mm2以上の断面積が必要です。ただし、ビニルコードではなくゴムコード(袋打、丸打など)を使用します。耐熱性が必要になるからです。
コードには色々な種類があり、特徴も様々です。
| コードの種類 | 特徴 |
| ビニルコード | 熱に弱いが一般的に使用 |
| ゴムコード(袋打、丸打など) | 電球線に使用 |
| 電熱用コード | コタツに使用 |
次の問題も周辺知識だけで十分に解けます。
問題
許容電流から判断して、公称断面積1.25mm2のゴムコード(絶縁物が天然ゴムの混合物)を使用できる最も消費電力の大きな電熱器具は。ただし、電熱器具の定格電圧は100Vで、周囲温度は30℃以下とする。
選択肢
イ.600Wの電気炊飯器
ロ.1000Wのオーブントースター
ハ.1500Wの電気湯沸器
ニ.2000Wの電気乾燥機
解説
断面積1.25mm2のゴムコードの許容電流は12Aである。イ~ニまでの使用電流値を求める。
電力[W] = 電圧[V] × 電流[A]から「電流[A] = 電力[W] ÷ 電圧[V]」で求めることができる。
イ.600Wの電気炊飯器・・・600W÷100V=6A
ロ.1000Wのオーブントースター・・・1000W÷100V=10A
ハ.1500Wの電気湯沸器・・・1500W÷100V=15A
ニ.2000Wの電気乾燥機・・・2000W÷100V=20A
計算結果は上記のとおりである。ここで12A以下の選択を選び、その中で最も大きい電流値を選べば正解となる。
答えは、「ロ.1000Wのオーブントースター」となる。
電線の許容電流に関する覚える量は少ない!まずはここから暗記して確実に得点源にしよう!
実現場でのお役立ち情報

周囲温度によって許容電流値は変わる
電流の許容電流の基準周囲温度は30℃。周囲温度が変わると実は許容電流値も変わってきます。参考に表を載せておきます。実際に現場で使う場合は、一般屋外やオフィスであれば、30℃で考えても問題はありません。
でも絶えず40℃や50℃の環境で使う場合は、許容電流値が下がるので気を付ける場合があります。許容電流ギリギリで使うと電線が熱を持ち、最終的には被覆が避けて短絡などの危険が伴います。
| 周囲温度 | 600Vビニル絶縁電線(IV) の許容電流減少係数 |
| 0℃ | 1.14 |
| 5℃ | 1.35 |
| 10℃ | 1.29 |
| 20℃ | 1.15 |
| 30℃ | 1.00 |
| 40℃ | 0.82 |
| 50℃ | 0.58 |
| 60℃ | 0 |
実際の危険な例2選
①ドラムリール

このドラムリールをよく巻いて使用すると思いますが、実は巻いた状態とすべて延ばした状態で許容電流の値が変わってきます。
- 巻いた状態は、5A。
- すべて延ばした状態は、15A。
「ドラムリール=15の許容電流」だけ覚えていると、巻いた状態で15A近い電流を流すと大変なことになります。
- ケーブルが熱を持つ。
- 最悪の場合、発火の危険性がある。

この考え方は、同一管内に電線を収納した場合の電流減少と同じ考えだよ!
ケーブルを巻いていると結局電流減少が起こるから許容電流も下がるってことだね!
大きな電流値を扱う場合はできる限り電線同士を離さそう!電流減少により、考えている許容電流より低い電流しか流せなくなってしまう。
②内部配線
製品の内部配線はなるべく細い方が使い勝手がよいです。理由は次のとおりです。
- 製品が小型なのでスペースがない。
- 配線の折り曲げが楽なので組み立てやすい。
しかし、でんせんサイズによって許容電流値が決まってきます。その考えを無視した電線サイズを選定すると大変危険なことが起こります。
- 電線が熱を持つ。
- 最悪の場合、発火の危険性がある。

製品で発火なんてしたら、会社の信用問題だけでなく、消費者の命にも関わるから大変。
各メーカーで選定基準を設けられていますが、許容電流を確実に超えない電線サイズを選定することが大切になります。
最後に:電線の許容電流の出題ポイントを押さえて最短合格しよう!

ポイントをまとめておきます。

電線の許容電流については、覚えることが多くありませんが毎年出題されているおいしい問題です。ぜひはじめに暗記して得点源になるように頑張ってください。
その他に出題傾向が高い問題は次の記事でまとめています。ぜひ読んで効率よく合格を目指してください。